新学年最初の定期試験が行われる、あるいは行われたころではないでしょうか。定期試験への取り組みと復習について、おさらいしておきましょう。
さて、今年度最初の定期試験です。
何度か書いてきましたが、学校の成績と受験の成績は間違いなく相関します。もちろん、授業がまったく受験と関係ないことをやっているとか、受験で使わない科目ばかりあるということになれば相関しない可能性もありますが、基本的に同じ科目である以上、高校に入ってしっかり勉強すれば、成績はあがるに決まっていますし、どんなに中学時代、あるいは小学校時代天才的であっても、初めてみるものをやらずに解ける天才はいません。必ず、すでにやっていること、あるいはそれを導き出すのに必要な知識を持っていることが前提になりますから、さぼっていれば、今、持っている知識では解けないところにいったとき、必ずできなくなります。
頭の良さはない、ということです。「遺伝が50%以上占めている」という研究結果がありますが、これは「同じ授業、同じ教育、同じ練習をしても、遺伝的な部分で差が出る」ということをさしています。当たり前です。決して、「勉強しても無駄」とか「勉強しなくてもできる」ということではありません。
したがって、一般人の感覚でいえば、「やればできるし、やらなければできない」が正しいと思います。
そうなると、最初の定期試験で、今年1年の自分のポジションや勉強の有り方が決まっていきます。
「塾で勉強してるから」という人。受験で使わない科目や、まだ塾でやっていない範囲であるなら、ともかく、受験で使うとすれば、どんなに範囲がずれていても、できるはずですよね?だって、あなたは塾でマスターしたはずだから。
どんなに塾型であったとしても、学校でやる受験科目については、よほど受験とかけ離れたことをやっていない限り、解けないとまずいんです。
ここが勝負どころ。もう一度確認しておきましょう。
- 試験準備をどのように行うか?定期試験の勉強は、受験勉強を意識して!
- 復習をどのように行うか?タイミングを逃さず、普段の学習方法を見直す。
- テストが終わったら、次のテストの目標をたてる!学習計画は、今日から始まる
試験準備をどのように行うか?定期試験の勉強は、受験勉強を意識して!
まだ、試験が始まっていない学校もあるかもしれませんね。まず、試験準備は、「受験勉強」として行うことが大前提です。
定期試験は、確かに出るところが決まっています。だから、出ないところは時間の「無駄」ですね。たとえば、古文で、「む」が出ていたとして、定期試験で重要なのは、「ここの意味・用法は何か」ですね。でも、受験勉強としては、
- 「む」には、どんな意味・用法があるかを全部言える
- そのうえで、ここの意味が言える
- なぜ、その意味に確定できるかを説明できる
- 似たようなものについて、説明ができる。たとえば、推量系の「べし」とか「らむ」とか「けむ」とか「めり」とか「まし」とか「じ」とか…
- そのうえで、他の助動詞も復習していく
ぐらいまで必要になるわけです。確かに定期試験としては時間の無駄ですが、受験勉強として考えた場合、今回切り捨てたものを受験までにまたやらなければならなくなるわけです。だったら、関連事項をまとめてやった方が、受験勉強としては早く終わるし、忘れにくい。
だから、まず、こうした気持ちで取り組まないといけません。
再現性はあるか?
こうしたことをチェックするのは、「再現性」はあるか?です。
数学だって、公式や例題など、まずは「覚える」という作業はあります。どんなに「手続き記憶」だとしても、身につけるようなものだとしても、それが「覚える」ものであることは否定できません。
でも、ここで必要なのは、違うところで出たときに再現できるかどうか。似たような違う場所、同じ知識を使う違う問題の時にできるかどうか。
できないとすれば、それは、「言葉の暗記」「記号の暗記」です。そうではなくて、「手順の暗記」にしないといけないし、「手順の暗記」も「意味や原理の暗記」にしないといけない。
時間がないからといって、それを力づくで覚えて、結局、意味や手順も覚えていないとすると、すぐ忘れてしまうし、覚えていたとしても、類題で力を発揮することはありません。
ノートだけでなく、元となる参考書に戻る!関連分野をきちんと復習
次に問題となるのは、勉強の元となるものです。定期試験では、「ノート」が主役になることが多い。それは、先生が「大元から厳選してノートに書く」からで、それが「試験にでやすいポイント」になるからです。
しかし、大事なことは、「ここでは用法が違う」から、試験には出ないけれど、本当は知らないといけないこと、ですね。
だとすると、参考書や問題集、場合によっては用語集や資料集など、先生が元にしていると思われるものに当たることは必須です。
ノートなんていらない。ノートは参考書の劣化版、です。
ノートが意味があるのは、あなたが自分の記憶を定着させるための手段である時です。
まとめノートを作るのは意味がある。ノートに書き出したり、マーカーを引いたり、絵を書いたりするのも意味がある。覚えたことを再現するのも意味がある。覚えるために何度も書いたり、思考をまとめるために、かきなぐったり、メモをとったりするのも意味がある。
しかし、出来上がったノートをコピーしてきてただ覚えるぐらいなら、参考書や原点をあたった方がいい。
確かに、英語や国語では、この試験範囲の「答え」がノートにあるのかもしれません。でも、だからこそ、答えだけを覚えるのでなく「手順」「方法」が大事なんですよね。
ノートだけ見直せば、いい点がとれる科目ほど、要注意。きっと先生が丁寧に板書してくれているんです。いい先生ですね。でも、そうなればなるほど、「本当に必要なたくさんの知識から、ここで必要なことだけが選り抜かれている」ということです。だから、効率が良くなる。
あえて、効率が悪いこともやらないと、模試で点数がとれるようにはなりませんね。
復習をどのように行うか?タイミングを逃さず、普段の学習方法を見直す。
試験が終わってしまったとしたら、やれることは「復習」です。
いい成績をとるにこしたことはありませんが、あなたの目標が、一般入試できちんと合格点をとって入学することだとすれば、ここでたまたま感が当たって、あるいはやったことが全部試験に出ていい点をとって、結局偶然でしかないのと、ここではできなかったけれど、悔しいから復習をして、ついにできるようになって、似たような問題なら解けるようになったのでは、実は後者の方がいいですよね。
というわけで、そもそも、「復習が大事」といいながら、たいてい、終わったことはどうでもよくなるわけですね。
でも、本当は、試験に向けて多少なりともやったわけだから、忘れないうちに反復すれば記憶が定着する可能性は圧倒的に高いわけです。
たとえば、さっき、「テストに出るところだけでなく、周辺もやるべきだ」と書きましたが、百歩譲って、試験でいい点を効率よくとるために、出るところだけをやったとしたなら、終わった直後に周辺をやれば、効率よく理解できるはずです。
でも、終われば、ね。
だからこそ、「タイミング」が大事だと書いています。テストが終わったら、しっかり復習する、当たり前のようにそういうことができると、成績はおもしろいほどあがりますよ。経験上。
だって、みんなが一番大事なのに、一番やらないところですから。差がつくんです。
テストが終わったら、次のテストの目標をたてる!学習計画は、今日から始まる
さて、さきほどの記事の後半は「分析」がテーマになっています。
できない問題には、あなたのここまでの学習方法の「癖」が反映されている、ということです。それをしっかり「分析」しないといけない。
とても大事なことです。
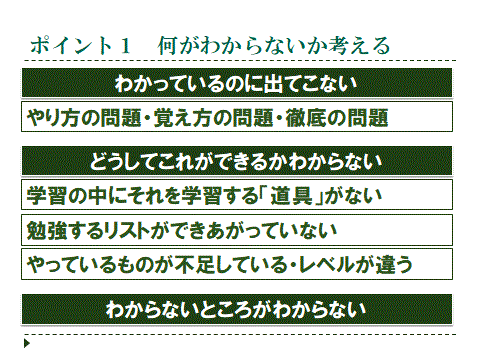
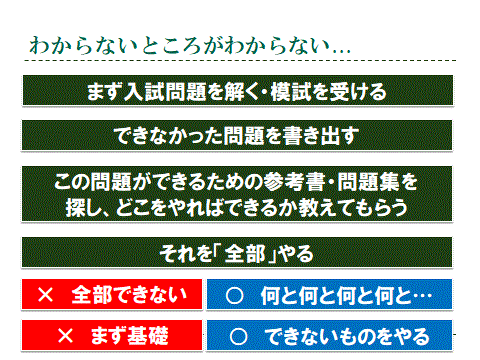

直感的にわかってもらえると思いますが、あなたが同じように過ごしたら、おそらく同じような結果が出るのです。得意も不得意もふくめて。
逆に、いつもと違う結果が出たとするなら、それは、前回と何か違うことがあったはずなのです。
学習方法や学習時間だけでなく、メンタルやモチベーション、友人関係や座っている席、日頃の生活にいたるまで、しっかりと確認して、悪くなったならそれを戻せばいいわけだし、良くなったなら、それを意図的に再現すればいいわけです。
特に、学習方法については、同じようなやり方をしている限り改善はできません。このあたりは、今、目標設定と学習計画を書いていますが、参考にしてください。
大事なことは、今回の結果は、「前回の試験後」「あるいは今までの全て」の「あなたの学習の仕方」が反映されたものだということです。決して、「試験前の勉強」の問題ではありません。
だから、すぐに次回の目標を明確にして、現状のやっていることを分析して、改善すればいいわけだし、そうすれば必ず結果が出ます。
私はいつも書きますが、まずは授業の受け方を変えること。試験前の学習の前に、日頃の家庭学習の前に、まずは授業の受け方を変える。一日何時間も授業で勉強しているのだから、ただ板書をノートに写す場ではなく、頭に入れる時間にしないともったいない。
その意味で今日、しつこく書いた「周辺情報」を復習するのも「授業」にしなければいけません。
だからこそ、今回の、最初の定期試験の結果が、今年1年を決める可能性が高いのです。あなたは今、授業の受け方や勉強の仕方が確立しつつある。たとえ、まったくしなかったり、平気で居眠りをしたりしていても、それが確立しつつある。なんとかしたければ、そこを変えること。
変えなければ、1年そのままです。
ここで変えられれば、1年上昇気流に乗ります。ここでひとふんばりしておきましょうね。